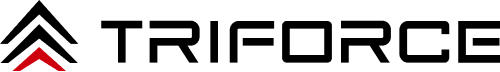営業職はAIに奪われる?AIツールの活用方法と成功事例を解説
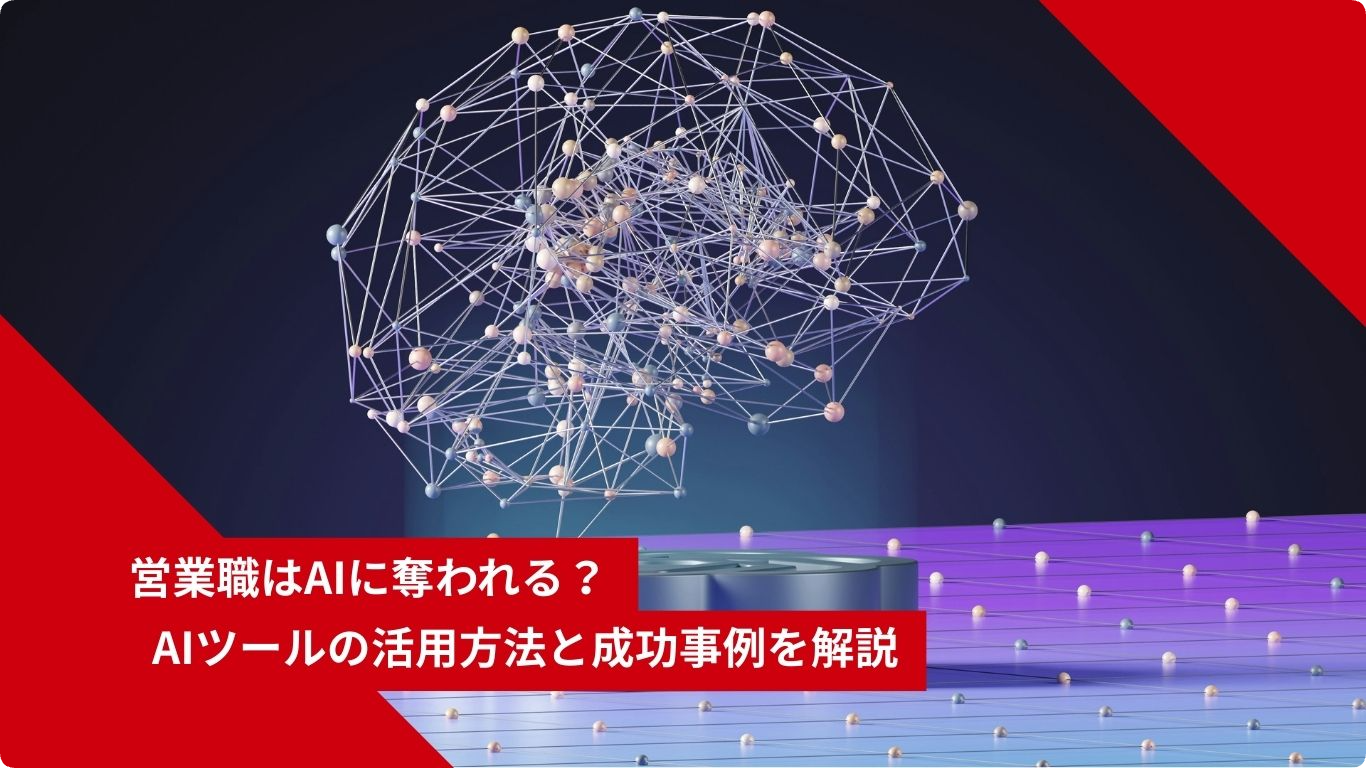
「分からないことは人に聞くよりもChatGPTに」のように、AI技術の発達が目覚ましい現在、そのような光景が日常になりつつあります。そんな中、セールス部門では、クライアント対応や、日々の資料作成業務などが多く、本来集中すべき営業が行えていないなどの悩みが多いのではないでしょうか?
また、AI技術の発達により将来的には「AIに仕事を奪われるのではないか?」そんな声を多く聞きます。
この記事では、営業職の現状と今後求められるスキル、営業職におけるAIツールの活用方法、そして実際に成果を上げている企業の事例までを徹底解説します!日々の業務見直し・効率化に少しでもお役立ていただければ幸いです。
目次
1.AIに奪われる?今の営業職のリアルな現状
2.これから求められる営業とは?
3.AIを導入するとは具体的にどうすればいいのか?
4.営業で使えるAIツールとは?おすすめツール5選
5.実際にうまくいっている会社は?AI営業の成功事例
6.まとめ
AIに奪われる?今の営業職のリアルな現状

営業職はAIでなくなるのか?信憑性のあるシンクタンクでは、「営業職そのものは無くなっていないが、営業職に求められる質がひと昔前と変わってきている」という見方が多いようです。理由を詳しく見ていきましょう。
営業活動の一部はAIに任せる時代に
最近の調査によれば、2026年までに営業関連のタスクの約60%がAIによる自動化が可能/実際に導入される見込みです。
引用元:セールスリーダーが知っておくべき77のセールスオートメーション統計(2025年) |ROMの

引用元:33 CRM 統計 2025 — 使用状況と市場シェア
近年の営業活動では、具体的に顧客リストの作成や商談後の議事録作成、メールの下書きといった定型業務がAIによって自動化されています。
特に、ChatGPTなどの生成AIやCRM/SFAツールの活用が進み、営業担当者はより戦略的でクリエイティブな業務に集中できる環境が整ってきました。CRMの普及は、以下のグラフをみても明らかです。
こうした変化は、営業活動の効率化だけでなく、働き方そのものの転換を促しています。
営業職そのものは消えていない
営業職は確かに変化していますが、「人との信頼関係を築く力」や「顧客の悩みに寄り添う力」など、人間ならではのスキルは依然として不可欠です。
AIが得意なのは情報処理やデータ分析といった部分であり、商談や交渉の最前線では、依然として人間の判断力や共感力が求められます。
つまり、営業という仕事は形を変えながらも、今後も重要な職種であり続けるのです。コロンビア大学の論文では、以上のことが具体的に述べられています。
求められる営業スタイルが変化している
従来の「足で稼ぐ営業」や「熱意だけで押し切る営業」は通用しにくくなってきています。現代では、顧客の課題を正確に把握し、最適な解決策をデータとロジックに基づいて提案するスタイルが主流です。
さらに、リモート商談の増加により、対面だけでなくオンラインでの提案力や資料作成力も求められるようになり営業の提案スピードも重要視される時代となっております。
そのため、機械的な処理はAIに任せ、本来人間が考えるべき柔軟で論理的なロジックに時間をかける必要があります。
これから求められる営業とは?

では営業スタイルが変化している今、どんな営業が今後求められるのでしょうか?
以下で、具体的に解像度を上げていきたいと思います。
AIと共存できる営業人材が今後の鍵。
「ツールを使いこなしながら、人間にしかできない信頼構築や提案力を発揮できる営業」が現在は求められていると言えます。データ分析や事務作業の自動化など、機械的な作業でただ時間がかかる作業などは、AIに任せ業務時間の効率化が重要です。
AIをうまく使いこなし、業務効率化を図ることで、顧客との関係構築や提案の質に時間を割くことができるようになります。
価値を発揮するのは、人間にしか成せない業です。
具体的にどんな業務が自動化できる?
営業の業務は多岐にわたりますが、中でも負担が大きく、自動化の効果が高いものを厳選して5つ紹介します。
導入すれば、時間削減・ミス防止・成約率向上が期待できます。
アポイント調整・日程確定
候補の日程をシステムが自動で提案し、お相手が選ぶだけでスケジュールが決まります。Googleカレンダーなどと連携して、予定の登録やWeb会議のURL作成も自動で完了。移動時間や希望の時間帯まで考慮できるので、調整ミスや手間を大幅に減らせます。
商談前準備・インサイト抽出
過去の問い合わせ履歴やウェブ上の行動ログから、お客様の関心ポイントや潜在的な課題をAIがまとめてくれます。そのおかげで、どんな課題にどうアプローチするかの仮説を立てやすくなり、商談準備の時間を短縮しつつ提案の質も高まります。 議事録・要約・ToDo抽出
オンラインでの商談内容をリアルタイムで文字起こしし、重要なポイントや決定事項、やるべきこと、担当者、期限まで自動で抽出。CRMへのタスク登録やフォローアップリストの作成も自動化できるため、議事録作成にかかる手間を大幅に省けます。
CRM入力・パイプライン更新
通話やメール、会議の内容が自動的にCRMに反映されます。商談の進捗フェーズ変更や次のアクション期限の設定、重複データの検知までサポート。入力漏れや更新忘れが激減し、これまで面倒だった記録作業がぐっとラクになります。
提案資料・見積書・契約書ドラフト
製品情報や価格、成功事例をもとに、見積書や契約書の下書きを自動で作成。表現の統一や条文の選択も行えるので、社内の稟議や承認フローもスムーズに進みます。資料作成にかかる初期の負担を大きく軽減できるのが嬉しいポイントです。
AIを導入するとは具体的にどうすればいいのか

「AIを導入したいけれど、何から始めればいいのか分からない」という声は多く聞かれます。ツールを導入するだけでは成果にはつながりません。ここでは、営業現場でつまずきやすいポイントも踏まえながら、AI導入の基本ステップを5つに分けて解説します。
① 活用の目的と対象業務を明確にする
まずは「どんな業務を、どんな目的で効率化したいのか」を具体的に整理しましょう。例えば「アポイント調整の手間を減らしたい」「週報作成の負担を軽くしたい」といった課題が挙げられます。そのうえで営業活動の全体を見直し、AIに任せられる業務と人が担うべき仕事をきちんと切り分けることが、成功のカギになります。
② ツールを調査・比較する
目的と対象業務が明確になったら、対応できるAIツールをいくつかピックアップして比較します。SFAや議事録作成、チャットボットなど、それぞれ特長や使い勝手は異なります。既存システムとの連携や操作のしやすさ、サポート体制などもチェックし、実際の業務に馴染むかを見極めましょう。
③ 小さく試して検証する
いきなり全社展開するのではなく、特定の業務やチームに絞って試験的に導入するのがおすすめです。例えば「議事録の自動化」や「営業メールの下書き作成」など、効果が実感しやすい部分から始めるとよいでしょう。導入後は、時間短縮やミスの減少などの指標をもとに、しっかり効果を検証することが大切です。
④ 社内で定着させていく
試験導入で手応えが感じられたら、徐々に全社展開へ。マニュアル作成や操作研修を充実させたり、よくある質問に答える体制を整えたりして、使いこなせる環境を作ります。成功事例や現場の声を共有することで、社内の抵抗感も薄れ、AI活用が自然なものになっていきます。現場と連携しながら進めることが、定着のポイントです。
営業で使えるAIツールとは?おすすめツール5選
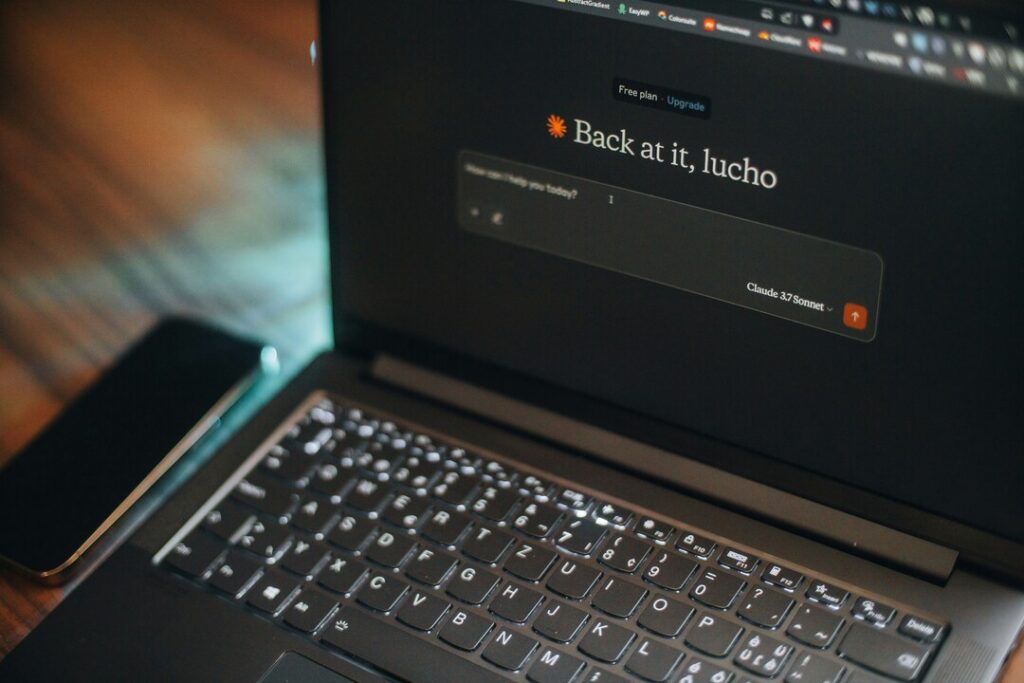
AIツール導入の必要性、効率化できる業務を見てきました。では具体的に、どのようなツールがツールが実用できるのでしょうか?
ChatGPT(提案資料や営業文書の生成AI)
営業提案書やアポ取りのメール、プレゼン資料の作成はどうしても手間がかかりますよね。そんな時、ChatGPTのような文章生成AIを活用すると、ベースとなる文書を素早く用意できるので大変便利です。文章の内容もしっかりしていて、表現の幅も広がります。特に、商談後のフォローメールを自動で作成するテンプレートとしてすぐ使えるのも大きな魅力。アイデア出しや言い回しに困ったとき「相棒」としても優秀です。
Mazrica、Salesforce (SFA・CRMの自動化ツール)
営業活動の「見える化」や「属人化の防止」に効果を発揮するのがSFA(営業支援)やCRM(顧客管理)ツールです。MazricaやSalesforceは、顧客ごとの対応履歴や進行状況を一元管理でき、誰が見ても現在の状況がすぐ把握できます。さらに、AIが商談の成功確率を分析し、次に何をすべきかをアドバイスしてくれる機能も搭載。こうした支援で、営業活動をより計画的かつ効率的に進められます。
HubSpot、Notion AI(営業メールの返信・下書き支援)
営業で意外に時間を取られるのがメール対応。HubSpotやNotion AIといったツールは、受け取ったメールの内容を理解して、返信文の候補を提案してくれます。そのおかげで返信がぐっと速くなりますし、テンプレートを
登録しておけば定型文の送信もスムーズ。ちょっとした表現に迷った時でもAIが複数の案を示してくれるため、精神的な負担もかなり軽減されます。
Musubu(リード獲得・ターゲット抽出ツール)
新規顧客開拓に苦戦している企業にとって、Musubuのような営業リスト自動生成ツールは心強い存在です。業種や地域、従業員数など細かい条件で企業を絞り込めるため、無駄なリスト作成の手間が省けます。さらに、接点のない企業へのアプローチも「反応が期待できるターゲット」に絞って行えるため、時間やコストをかけず効率よく成果を上げやすい見込み客に集中できます。
実際にうまくいってる会社は?AI営業の成功事例

AI営業の導入に不安を感じている方も多いですが、実際に成果を上げている企業も多数存在します。ここでは3社の事例を紹介します。
大塚商会
大塚商会は、営業のデジタル化にいち早く取り組んでいる企業のひとつです。
SFAやAI分析ツールを導入し、営業担当ごとの受注傾向や成約のパターンを可視化。特に注目されているのは、AIが「次に狙うべき顧客」や「最適な商談タイミング」を提案してくれる機能です。
こうした仕組みにより、これまで担当者の経験や勘に頼っていた営業判断が、データに基づく戦略に置き換えられています。
その結果、受注率の向上や、新人営業の早期戦力化にもつながっています。
みずほ銀行
みずほ銀行では、法人営業の現場にAIを取り入れ、対応スピードと提案の質を大きく高めています。
具体的には、AIが過去の取引データをもとにニーズを分析し、顧客ごとに最適な商品を自動で提案。FAQの対応や営業メールの下書きにもAIを活用することで、営業担当者はより付加価値の高い提案やコンサルティングに集中できる体制が整いました。
これにより、顧客満足度も向上し、同行の営業力は大手銀行の中でも高く評価されています。
星野リゾート
星野リゾートでは、法人・団体向けの営業活動にAIを活用し、提案業務の効率化を進めています。
たとえば、過去の予約履歴や季節ごとのトレンドをAIが分析し、「この時期、この企業にはこのプランが効果的」といった提案を自動生成。また、ChatGPTを活用した提案書のドラフト作成も実施しており、営業スタッフはヒアリングや現地案内といった、より人との関わりが重視される業務に時間を使えるようになりました。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
この記事では、営業職の現状と今後求められるスキル、営業職におけるAIツールの活用方法、そして実際に成果を上げている企業の事例までを解説してきました。
営業職はこれからもなくなることはありません。しかし、今後の営業には「ツールを上手に活用しつつ、人間らしい強みを発揮する力」が欠かせません。
資料作成やメールのやり取りなど、手間のかかる作業はAIに任せて、その分、「信頼関係の構築」や「お客様の課題を深く理解すること」、「状況に応じた柔軟な提案」といった、人にしかできない部分に集中することが大切です。
AIと共存しながら成果を出せる人材こそ、「これからの時代に選ばれる営業」です。
日々の業務見直し・効率化に少しでもお役立ていただければ幸いです。